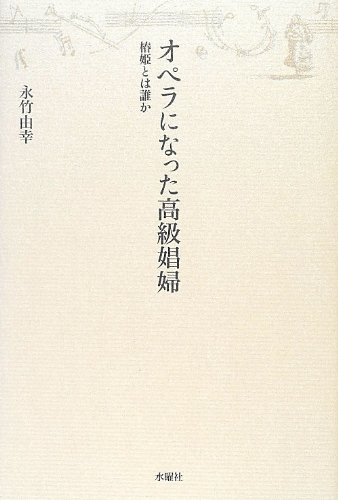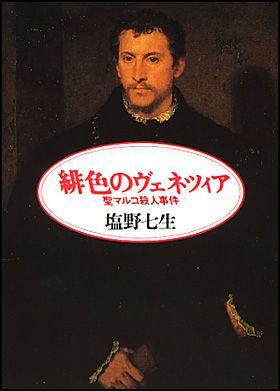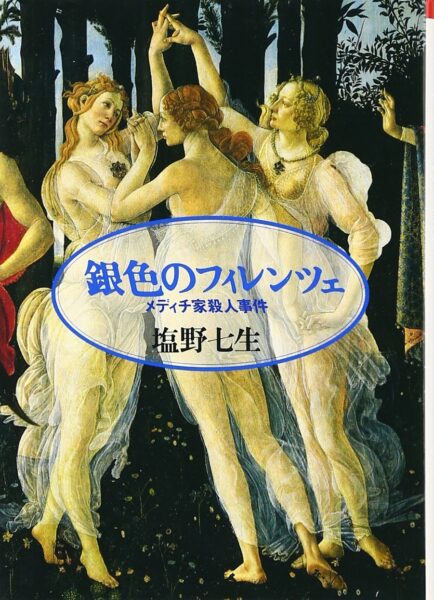なんだかずっとクルティザンヌにこだわっているようなんで恐縮ですが。
かのオペラ研究家、故永竹先生が書かれたご本で『オペラになった高級娼婦〜椿姫とは誰か〜』というものがあります。
その中で先生は高級娼婦文化は人類史上3回のみ発生していると仰っています。
■一回目■
古代ギリシア。 アテネでは貴族達が哲学の話をするサロンに集まることがいちばん「イケてる」ことでした。半裸の男性が酒飲んじゃ哲学談義ってどんな状況なんでしょうか、流行ってる時はとにかくそれが一番かっこよく見えるんでしょう。
通常、そういうところは細君であっても女性の立ち入りは禁じられていました。そして、唯一、『ヘタイラ』と呼ばれる高級な遊女のみが立ち入れたということが残されています。
まあ、かつての永田町あたりでは赤坂の高級料亭で政治が行われ、そこに立ち入れるのは芸妓と女将という『プロの女性』だけ、というようなところでしょうか。
さて、一方、アテネ市民とは『アテネ市民との婚姻で産まれた子供』しかなれません。
そのため、女性を
- 嫡子(市民)を産んで育てる役割の正妻
- 通常の身の回りの世話をする側室
- 正妻を持つ事ができない貴族以外の男性を平等に面倒見る娼婦
- ヘタイラ
とわけたそうです。
ヘタイラとは『外国人であり、美貌と教養を持ち、子供の世話や日々の世話をするようなことにとらわれず男性と同等の知恵と知識を持ちサロンにつれて歩ける女性』という存在だそうです。元々の言葉の意味も(連れ)という意味から発生したと言われています。なんでまた「外国人限定」なんでしょうね。
さて、ローマではどうしてこういった文化が残らなかったのでしょうか?
それは「異民族の集合体であること」と「女性が強かった」から。
サビーヌの略奪の歴史に見るように、自分の夫を守るために父や兄の軍隊の前に飛び出す勇敢な女達が居るくらいです。
ギリシャ型正妻なんざ、やってはくれません。
なので、アテネ没落後はヘタイラ文化は消えました。
さらにローマがキリスト教化されることで自然神崇拝のおおらかな人々を、キリスト教的戒律で雁字搦めにしたお陰で、女性はあくまでも原罪として表舞台にできるだけ出ないようにされてきたのです。
それなのに二回目がある。 どこで?
■二回目■
それは『ルネッサンス時代のローマ』です。なんと!仇敵、キリスト教の総本山で発生するのです。
『コルティジャーナ』。
クルティザンヌの語源ともなる言葉で、『宮廷貴婦人』とでも訳しましょうか。
法王庁で当時多くの人文学者や知識階層があつまり自由な討論が繰り広げられたのですが、さすが法王庁は(裏はどうであれ)完全な男社会です。
また性懲りもなく「なんだかオトコだけじゃあどうも殺風景だねえ。」って誰が言いだしたかは知りませんが、やはり女性を配しましょう!ということになりました。
参加者の夫人や娘達はそれなりに教養はありますが、さすがに独身だらけの法王庁サロンには出入りしにくい。
そうなると、知恵を絞るモノには天啓がくだされるのです。
そうだ!古代のヘタイラを復活させよう!!
だって、『ルネッサーンス』だもんね。
かくして、庶民の中で美貌(なんで必要なんかな……)と頭脳が明晰な少女達を選び出し、徹底して教育をして育て上げた結果、最上級の宮廷婦人、コルティジャーナが完成します。
彼女達はサロンに出入りする貴族達の愛人としてどんどん成功を収め、引退の年頃になる頃にはひとかどの財産を築き上げるものが多かったと言われます。
そのためどこかの国のステージママのように、自分の娘がちょっと可愛いとなると、やっきになってコルティジャーナにならせるべく目の色をかえるようになりました。
ああ…… 当然風紀が乱れますよね。 深読みしなくても。

そのせいとばかりは言えませんが、原因のひとつとして宗教改革の嵐が置き、法王庁からコルティジャーナ達は追放されます。
そして、宗教からも政治からも自由な唯一の都市、ヴェネツィアで再度花開きます。
ヴェネツィアでは、コート(宮廷)や法王庁はありませんので、自分の才覚だけでサロンを開き、そこであらたな文化を広めます。
塩野七生さんの小説「緋色のヴェネツィア」「黄金のローマ」では、この時代のコルティジャーナを重要なキャラとして扱っています。
歴史物で有名な塩野さんですが、この三部作は軽いミステリータッチの読み物としてもとても面白いのでお勧めです。
当然、ヴェネツィアの没落とともにその存在も消えて行ったのです。
■三回目■
これは言わずと知れた、椿姫の舞台となった1830年代〜45年頃のフランスです。
パリのクルティザンヌと比べると、前期2回の方がすごみがあったような気もしますが、きっとそれは社会の中で、他の手段をもって女性がのしあがる選択肢が増えてきた、ということになるかと思います。
日本の花魁、特に吉原や京都の島原の太夫にも通じるものがありますが、似て非なる最も大きなところは、花魁の所有権はあくまでも店が持っていたのです。
すべて三回とも、女性そのものの所有権はあくまでも、女性本人が持っていたということです。
オペラになった高級娼婦 椿姫とは誰か
【ご参考までに】高級娼婦が生まれた歴史と背景を、オペラから見る当時の風俗から「椿姫」の主人公の姿を解き明かす一冊。
著者の永竹由幸氏は歌舞伎やオペラの評論家として高明な方ですが、それ以前にヨーロッパの歴史について広く深い知識を持っている方のため、椿姫が登場するまでに長く広い歴史が積み重ねられていることがわかる本です。
緋色のヴェネツィア: 聖マルコ殺人事件
【ご参考までに】すでに絶版となっており、Kindle版も出ていないので、中古か図書館で見つけていただくことになるとは思いますが、本当に面白いです。主役のマルコの周りに現れる遊女オリンピアこそ、ヴェネツィアで出現したコルティジャーナそのものです。タイトルに「殺人事件」とありますが、ミステリー要素は弱く、歴史とヴェネツィアの深く面白いお話がてんこ盛りです。
銀色のフィレンツェ: メディチ家殺人事件
【ご参考までに】16世紀のフィレンツェが満喫できます。 ヴェネツィアのマルコが主人公。フィレンツェは作者の塩野七生氏が永く住んだ街だけあって、内容も一段と濃くなっています。共和制をしくヴェネツァからやってきたマルコが出会う人々は、少し落ち目になったとはいえ、君主制を敷くメディチの人々やヴィットーリのような政治の世界の人々。もうそうなったら作者の本領発揮です。また、フィレンツェの旅行ガイドとしても秀逸です。
本当に絶版になったのが惜しい!
黄金のローマ: 法王庁殺人事件
【ご参考までに】最後はローマ。黄金のローマの名前の通り、この舞台の時代はちょうどミケランジェロがシスティナ礼拝堂の壁画を描いているまさにその時代。ローマがまさに黄金の輝きを見せていた時代です。ガイドブックにさえ載っていないないような銅像の逸話なども魅力です。そして、ヴェネツィアで登場したコルティジャーナのオランピアの秘密がここで。